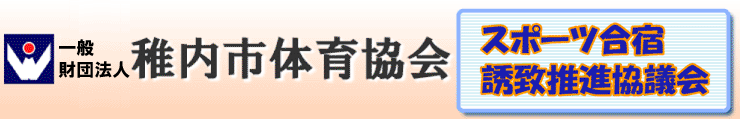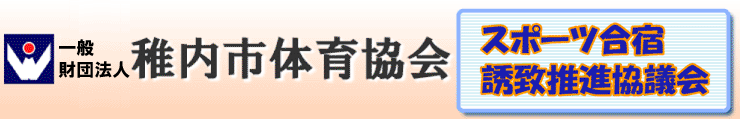| 【研究協議】「テーマ:スポーツ活動の継続と関係機関との連携」 |
提言者:加賀 誠 氏 <稚内東中学校教頭>
中学校の運動部活動は生徒数の減少もあって、種目によって異なるが部員の確保が困難になってきている。スポーツ少年団から多くの入部が期待できる場合は、当面の活動も充実し保護者の熱い支援も期待できるが、その逆の場合は部の存続も懸念される現状である。生徒の健全な育成を助長する手段としてスポーツ活動が重要度を増す中、小学から中学・高校へと継続したスポーツ活動で、指導者間や保護者とのつながり、競技団体との連携が重要である。
本日は、昨年度まで近隣の小さな町の学校で、部活動顧問として指導していた際のスポーツ少年団や競技団体との関わりや保護者との対応と現状を比較しながら、継続性のある充実したスポーツ活動のための様々な思いをお話しいただきます。 |
提言者:出口 昭仁 氏 <稚内中央小学校PTA会長、稚内市連合父母と先生の会会長>
少年期は町内会の野球チームに所属し、近所の友だちとともに白球を追いかけ、高校ではバスケットボールに励み、スポーツの楽しさや素晴らしさを体験していた。保護者の方々は、子ども達の成長にスポーツ活動が有意義であることを理解していると思うが、学校以外の様々な活動でスポーツに触れる機会の少ない子ども達も少なくない。そこで、本日は、スポーツ少年団という組織やその活動がどのように映っているのか、またどのくらい理解されているのかを、学校PTAという親の立場からお話しいただきます。 |
提言者:倉 弘子 氏 <稚内水泳スポーツ少年団代表指導者>
6年生卒業と同時に退団となるスポーツ少年団が多い中、稚内水泳スポーツ少年団は、中学・高校に水泳部がないこともあって、小学校から中学・高校へと継続したスポーツ少年団活動が展開されている。また、充実した指導体制で、団員の目的に応じた班の分類など、楽しむコースと選手コースとに分けた指導で、近年では全国大会出場選手も頻繁に輩出される団体へと成長した。年中使用できる施設での活動も大きな要因ではあるが、ここに至るまでの様々な苦労を力として、一貫指導体制の構築や育成会、学校との連携をもったモデル的なスポーツ少年団で、これまで克服した課題や取組んできた事例をご紹介いただきます。 |